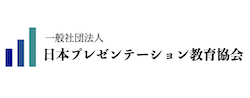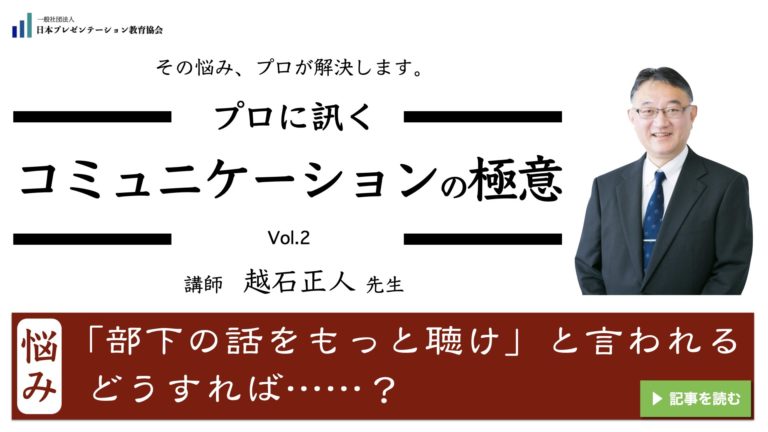こんにちは。日本プレゼンテーション教育協会の代表理事・西原です。
「プロに訊く極意」第2弾は「コミュニケーションの極意」と題してお届けします。毎回、協会に寄せられるプレゼンやコミュニケーションに関する質問や、受講者の悩みなどを1つ取り上げて、それについて各界で活躍する様々なプロ講師・専門家にインタビューして、いろいろな視点からアドバイスいただきます。共通するアドバイスあり、独自の切り口で解決する方法もありで、きっと現状の打破するヒントになること間違いなしです!
さらにPodcastで、プロ講師から直接学べる!
本連載の連動企画として、アドバイスいただいた講師が、聞いて学べるPodcast「めっちゃ!伝わるプレゼン」のゲストとして登場。協会代表の西原が直接アドバイスを伺います。読み終わった後に聴けば、さらに学べること間違いなしです。
【今回のお悩み】
上司から「早合点することが多い」「早とちりを治せ」と言われます。
また、周りや部下が「あの人は人の話を全く聞かない」と言っていた、とも聞かされました。
どうすればいいでしょうか?
家電メーカーで働く技術者のBさん(52)は、調理家電部門の開発リーダーとして頑張っている。
ところが、周りとのコミュニケーションがどうも上手くいかない。先日も部長に呼び出され、「早合点することが多い」「早とちりを治せ」と言われました。さらに周りや部下が「あの人は人の話を全く聞かない」と言っていた、とも聞かされました。
Bさんの悩み
・相手の話の途中で、だいたい何を言いたいのか理解できるので遮って答えたら、相手に嫌な顔をされる
・プレゼンで相手の質問に答えたら「そうじゃなくて……」と言われる
一体どうすればよいのだろうか……?
【早合点】
十分に理解しないうちに、わかったと思い込むこと。早のみこみ。「―して期日を間違える」【早とちり】
大辞泉
早合点して間違えること。「―が多くて困る」
今回、アドバイスいただく先生

工学博士
キャリアコンサルタント(国家資格)
産業カウンセラー
越石 正人 先生
聞き手:西原 猛(日本プレゼンテーション教育協会 代表理事)
今回アドバイスいただくのは、原子力発電の研究開発業務に長く従事し、国家プロジェクトを含め、数多くの研究開発プロジェクトのマネジメント経験も持つ越石先生。マネジメントのみならず、自ら研究を行うべく工学博士の資格を取得し、論理的思考に磨きをかける。さらに、人としての感受性を磨くべく、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントの資格を取得。マネジメント、論理的思考、心理学といった幅広い分野の経験と専門知識を持っている。

相手の話を100%理解することは難しい
越石先生は先ず、基本的な心構えとして「相手の話を100%理解することは難しい、ということを理解してください」と話す。
「相手の話には、客観的事実のほか、主観的なもの(意見、考え方、気持ちなど)が含まれます。このうち、相手の主観を理解することはとても難しいものです。これはBさんだけでなく、すべての人にとって難しい課題です」
コミュニケーションの原則は「相手は自分とは違う」。しかしこれを忘れて自分の主観で人の話を聞いてしまいがちだ。そうすると、最後まで話を聞かず、途中で分かったつもりになって人の話を早合点してしまう。では、Bさんのように早合点しないためにはどうすれば良いだろうか?