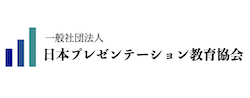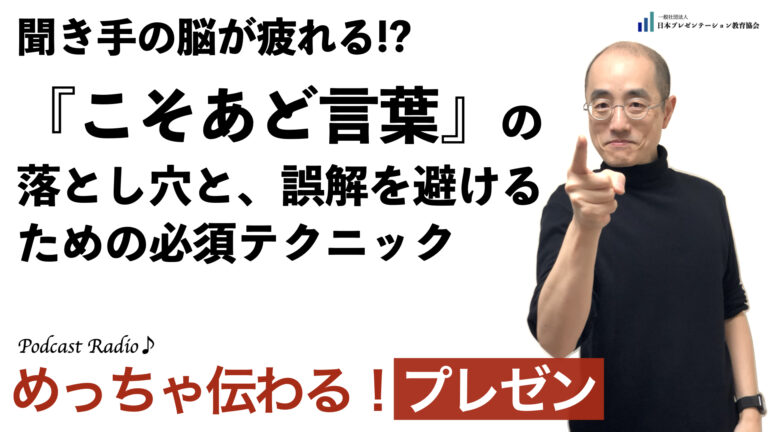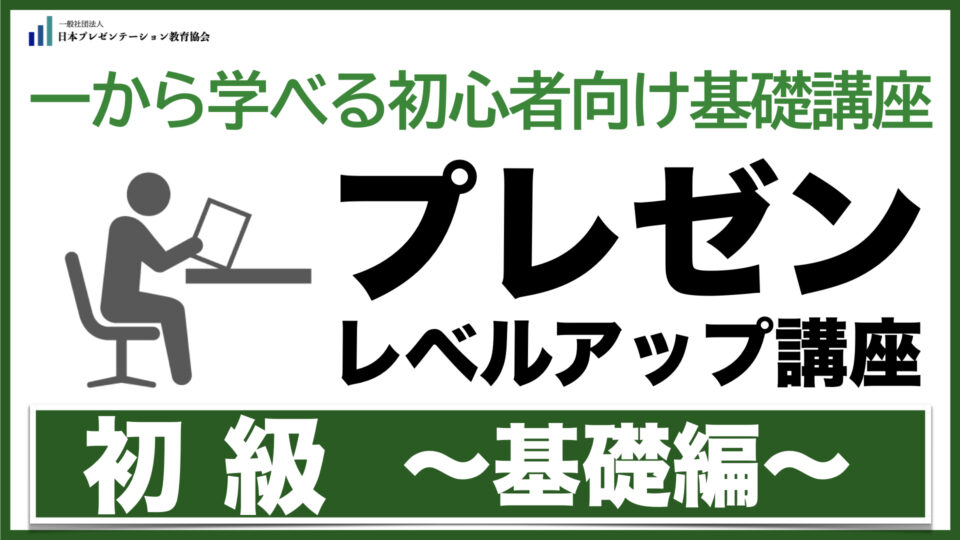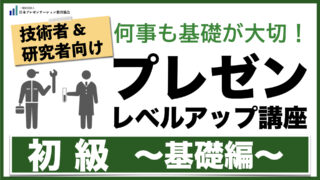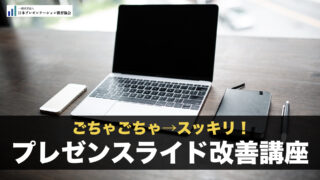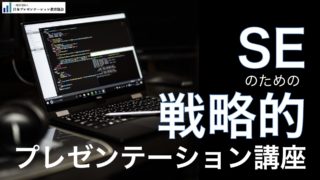プレゼンの基礎知識が音声で学べるポッドキャスト番組「めっちゃ伝わる!プレゼン」。
今回のテーマは「こそあど言葉」の落とし穴。これをちょっと深掘りして行きたいと思います。プレゼンとか、 日々の会話でもなんとなく”あれ”とか、”それ”って結構無意識に使っていますけど、これで本当に伝わっているのかなって気になることはありませんか?なんか説明がわかりにくいかも……とか。
それで結局、何が言いたいの?みたいに相手に思わせてしまう時は、もしかしたらこのすごく身近な「こそあど言葉」の使い方が鍵になってるかもしれません。
そこで「こそあど言葉」の基本からその便利な側面、それから思わぬ落とし穴についても触れて、さらにはもっと上手に使いこなすためのヒントまで一緒に探っていきましょう。
こそあど言葉
指示語(しじご)の総称。人や物、場所、方向、状態などを指し示す働きをする言葉で、「これ・それ・あれ・どれ」の頭文字をとって名付けられた。文章や会話の中で、同じ言葉を繰り返すのを避けたり、話し手と聞き手からの距離や文脈によって、指し示す対象を明確にする役割がある。
1.指示代名詞 (物・場所・方向を指す)
これ、ここ、こちら/それ、そこ、そちら/あれ、あそこ、あちら/どれ、どこ、どちら
2.指示連体詞 (名詞を修飾する)
この (本)、こんな (人)/その (本)、そんな (人)/あの (本)、あんな (人)/どの (本)、どんな (人)
3.指示副詞 (動作・状態を修飾する)
こう (する)、そう (する)、ああ (する)、どう (する)